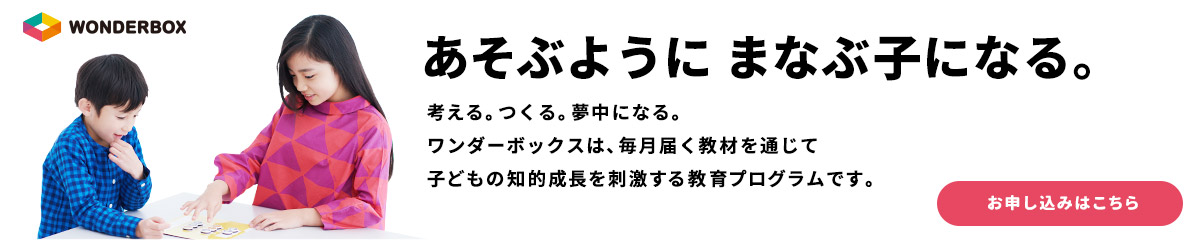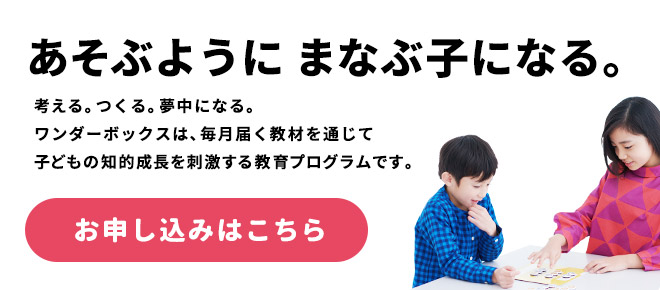2022.05.31
始めやすくて奥深い、トイ教材「コインズカルテット」の対戦ゲーム「コインでたいせん!」紹介
活用方法のヒント
Vol.シンチャオ(6月号)のトイ教材「コインズカルテット ベーシック」の冊子には、家族で楽しめる対戦ゲーム「コインでたいせん!」があります。
4歳〜(年中・年長)向けには「コインレース」、6歳〜(小学生)向けには「コインレース」と「ポイントがっせん」が収録されています。
今回の記事では、「コインでたいせん!」を通じて育まれる思考力、初めてやるときにつまずきやすいこと、より深く楽しみたいときのポイント等を、コンテンツクリエイターに聞いてみました。
いかに速くゴールまでたどり着くかを競う「コインレース」

山からコインを1枚とる→黄色なら1マス、緑なら2マス、青なら3マス進む→先にゴールした方が勝ち、という、すごろくにも似たシンプルなゲームです。サイコロではなく2つのコインの山で進むマスを決めていくことで、どんな面白さが生まれるのでしょうか。
運営チームからの質問に、コンテンツクリエイターに答えてもらいました。
Q1. 「コインレース」を通して、どのような力が育まれますか?「ここが面白い」というところも、あわせて教えてください。
A1. 自分が特定のマスを踏まないように歩数を計算すること、相手にどのコインを「取らせるか」を考えることを通して、最適な戦略を論理的に詰めていく思考力が育まれます。
「コインレース」は、「どちらかのコインを選ぶ」というシンプルな操作でありながら、考えることが多様にあり、戦略的な思考が重要になるゲームになっています。

例えば上の状況で赤のコマの番で、数としてはよりゴールに近づけそうな「緑(2マス進む)を選ぶと「3マス戻る」に着いて逆戻りしてしまいます。一見損をする「黄(1マス進む)」を選ぶと、相手のコマの上に止まってもう一回進むことで逆転できます。
山が2つあることで、どちらを取れば自分が有利になるかを考えるところに、このゲームの面白さがあります。
サイコロを使ったすごろくと違い、このゲームでは、一度山を作ってしまえばその山の中でコインの順番が入れ替わるようなランダムな要素がなく、有利不利は純粋に戦略によります。
Q2. はじめてやるときに、つまずきやすいところはありますか?
A2.どの色で◯マス進むという対応関係や、相手のコマの上に乗ったときはもう一度進める点は見落としやすいかもしれません。
色と進む歩数の対応は、慣れるまで把握するのに時間が必要ですが、何度かやっていくことで覚えられるようになってくるでしょう。

動かすコマもコインなのが紛らわしく感じてしまう場合は、コインの代わりに消しゴム等をコマとして使ってみてください。
相手のコマの上にコマが止まったときはもう一度自分の番になるというルールは、盤面の方に書いてあるので、注意して読んでいただければと思います。

Q3.慣れてきた頃におすすめの、よりステップアップした遊び方を教えてください。
A3.次の相手の番のことを考え、相手が歩数の少ないコインを取るように、あるいは「3マスもどる」を踏むように、自分が取るコインを選ぶのも有効な戦略です。
例えば、1枚目の図(左)の状況で赤のコマの番のとき、黄を取って1マス進み相手のコマに乗ってもう1回進むのと、青を取ることで2枚目の図(右)のように青のコマ(プレイヤー2)に黄を取って3マス下がるように強いるのは、どちらが有利でしょうか。このように、一見シンプルな要素が重なり合うことで、深い戦略性が生まれます。
終盤では、山が1つになるとその後の動きが確定するため、先読みして「片方の山の最後の1枚をいつ取るべきか」を考えると、より勝利しやすくなるでしょう。
他には、「相手のコインに乗るように取るコインを選ぶ」、「相手の作戦の選択肢を減らすため、両方の山の一番上のコインが同じ色になるようにする」「片方の山がなくならないように、多い方からコインを取る」など、色々な戦略があります。
ルールをアレンジしてみるのも大歓迎です。
「差が出すぎないように青も2マスにする」、「逆転が起きやすいようにゴールまでのマスを増やす」「6マスもどるマスを設ける」など、「こうしたら面白くなるかも」と思ったものをぜひ試して研究してみてください。
6歳〜(小学生)向けの「ポイントがっせん」については下記をクリックしてご覧ください。
以上、「コインでたいせん!」の紹介でした。この記事が、シンプルさと発展性を備えた「コインでたいせん!」を、より楽しむ一助となれば嬉しいです。