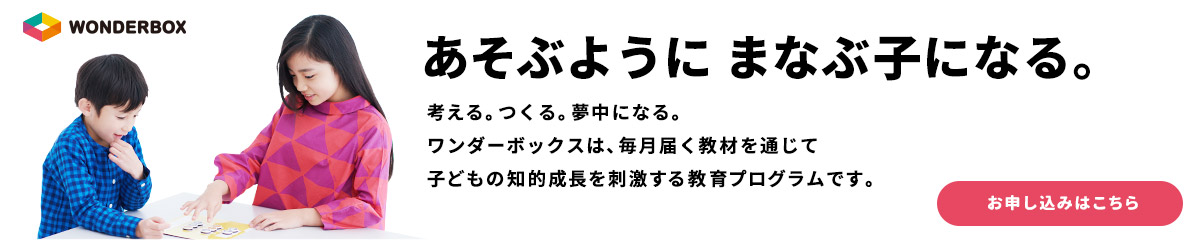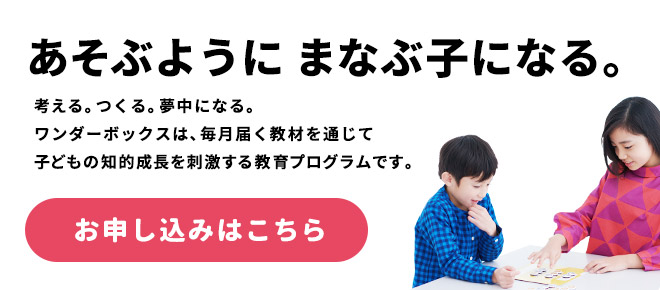2022.12.27
「子どもにはなぜ思考力が大切?」花まる学習会代表 高濱氏×弊社代表 川島 12/8(木)対談イベントレポート
12/8(木)に行われた、オンライン対談イベントのレポートをお届けします!
「子どもにはなぜ思考力が大切?『楽しく学ぶ』ために大人ができること」をテーマに、30年以上にわたり授業や野外体験で思考力を育む学びを追求してきた 花まる学習会代表 高濱氏と、高濱に学びSTEAM教材「ワンダーボックス」を開発してきた弊社代表 川島が対談し、保護者の方の疑問を解決する一助となるようイベントを開催しました。
ワンダーボックスの教材内容についてもお話ししています。
※対談の中では、「思考力」 のことを「考える力」とも表現しています。

・花まる学習会 代表 高濱正伸
花まる学習会代表。1959年熊本県生まれ。県立熊本高校卒業後、東京大学に入学。1990年同大学院修士課程修了後、1993年に「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を重視した、小学校低学年向けの学習教室「花まる学習会」を設立。「情熱大陸」(毎日放送/TBS系)、「カンブリア宮殿」(テレビ東京)などドキュメンタリー番組にも出演し、注目を集めている。現在、算数オリンピック委員会の理事も務める。
・ワンダーラボ 代表 川島 慶
東京大学大学院修了。2007年より花まる学習会で、問題集「なぞぺ〜」制作。開発した思考力育成アプリ「シンクシンク」は世界150カ国170万ユーザー、「Google Play Awards」など受賞多数。算数オリンピックの問題制作に携わり、2017年より三重県数学的思考力育成アドバイザーも務める。
思考力ってなぜ大事?

(代表川島、以下川島)
思考力とは何かというと、「1を聞いて10を知る」もっというと「未知の課題に遭遇したときに手持ちの道具で課題に立ち向かう力」だと考えています。これからますます先行きが不透明な世の中になっていく中で重要な力だと思っています。
(高濱氏、以下高濱)
定義は本当にその通りですね。
「思考力が大切」というのは当たり前、といえばそうなのですが、幼児期は学習の「基盤」といわれる、例えば足し算、割り算、漢字演習などをはじめとする内容にフォーカスされることが多いです。
しかし、「本当に大切なのは「頭のよさ」の部分。
それは、少し嫌になりそうなことでも論理的に楽しく考え続けられる力のことです。つまり、「思考力」ですね。

「基盤」の学びがいらないのではありません。花まる学習会でも取り組みます。幼児期は「頭のよさ」につながる、考えることへの「肯定感」を育むことに時間をかけ大切にしましょう。
つまり「考えることが楽しい!」という状態ですね。考えることへの「肯定感」が育まれると、難しい問題がきて解けずに苦しいときも「自分で解きたい!」という気持ちで取り組むようになりますよ。
大切なのはたったこれだけです。
そして考えることへの「肯定感」を育むには、「遊び」の中に取り込むことができるといいですね。
思考力はどうしたら育まれる?

「考えることが楽しい」と感じる問題にたくさん触れてほしい

(川島)
弊社が開発している通信教材「ワンダーボックス」では、子どもたちが考えることが楽しい!と感じられるように教材を開発しています。
トイ教材「カラコロキューブ」の中に収録している「カラコロモンスター」は、6色4つのキューブを組み合わせ、アプリと連携して16個のモンスターを集める教材です。
この「カラコロモンスター」は、算数でいう「場合の数」という分野において、とても最適なアプローチだなと感じています。
(高濱)
中学入試において、例えば立体問題などはパターン化して解かせることで、苦手な子どもでも解けるようになります。ただ、「場合の数」だけは、とことん差がつく分野です。本当の頭のよさは「場合の数」ででるなと感じています。
考える力の肯定感を育むには「これもあるぞ!これもあるぞ!」と考えることを楽しみながら取り組むことが大切です。それがまさにできる教材だなと思います。

(川島)
もう一つ、私が開発に携わったアプリ教材「ケミーのじっけんマップ」は化学実験をテーマにしています。
草と粘土と砂という限られた素材(手持ちの道具)を使って、コップと茶碗を作るという課題に取り組みます。「これとこれを組み合わせたらどうなるか」を考えて試しながら、「?」の部分を明らかにしていきます。
試行錯誤する中で、目的のものを目指したり、寄り道の実験を楽しみながら考える力を育むことができます。
(高濱)
「手持ちの道具でなんとかしたい」という子どものモチベーションを作るのは大人の仕事ですが、なかなかその動機を子どもへ与えることは難しいですよね。まさにこの教材は具体的な方法だと思います。
できれば、ご家庭で実際に作ってみるといいですね。汚くても形にしてみると本当にわくわくしますから。
(川島)
私が考えることが好きになった理由は、父方の祖父は将棋、母方の祖父は囲碁が好きだったんですね。小学校低学年のときは興味を持たなかったのですが、「おじいちゃんがこんなにハマっているものは、どんなところが楽しいのかな?」とずっと思っていました。
その後、高学年になって、面白みが理解できるようになりハマったのですが、その経験から「大人が楽しむ」というのも大切だなと思います。
(高濱)
そこで大事なのは感想戦ですね。「どうしてそうしたのか」必死でやった勝負だからこそ、子どもたちに食い込むんですね。
やりっぱなしにしない。これが大人にできるいい環境づくりの一つです。
「大人にできること」は何?

(川島)
私が高濱さんと同様に影響をうけた方に、中高の恩師である井本先生がいます。
その井本先生が考えることを好きになった瞬間を自分で覚えている、という話が印象的です。
幼少期に、いわゆる「植木算」で間違ったときに「え?」っと思って「なんで?」を考え、「あ!そうか!」とわかった経験から考えることが好きになったと言っていました。
幼少期に、いわゆる「植木算」で間違ったときに「え?」っと思って「なんで?」を考え、「あ!そうか!」とわかった経験から考えることが好きになったと言っていました。
このように、間違ったときこそ、知的わくわくの大チャンスで、大人から子どもへは「間違えてもいいんだ」ということを声かけできるといいなと思います。
(高濱)
このなるほど!という、わかったときの快感を感じることが重要です。この経験を積み重ねることで、考えることへの「肯定感」が育まれていきます。
肯定感に焦点を当てながら、この「わかっちゃった体験」を積んでいく。目の前の正解・不正解に一喜一憂しなくて大丈夫です。
そして、子どもが間違ってしまったときの声かけとして、子どもの心に寄り添ってあげることが肝です。咎めたり評価されたりすると反発してしまいます。間違ってしまったときに「こういうふうに考えたから間違えたんだね」「くやしかったね」という声かけがおすすめです。
心がしなやかな小学校低学年までに、肯定感をつけていくことが大切です。
教育業界に40年いた経験から、子ども自身に肯定感さえ育まれていれば、逃げていた時期があったとしても後から自分で「やるよ!」といって学んでいきますよ。