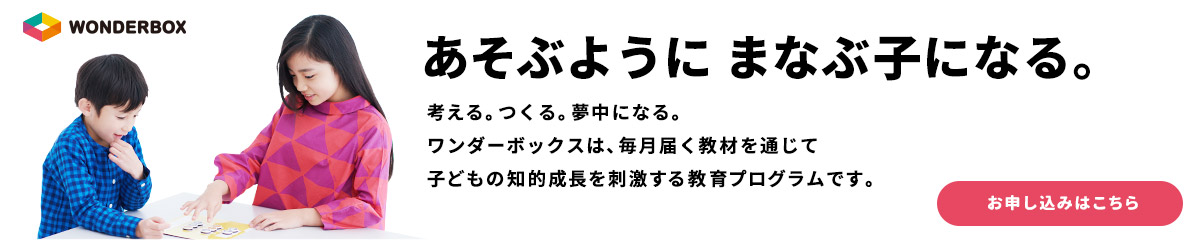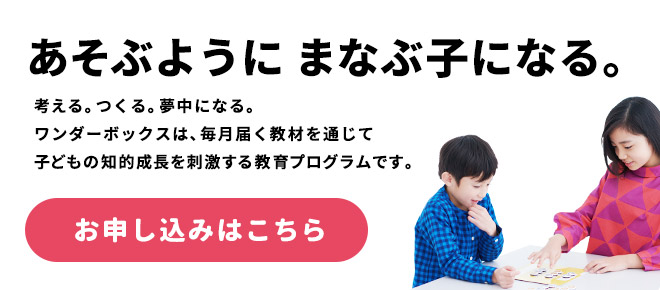「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」は科学法則を楽しく体感できるアプリ教材です。
今月号のテーマは「風」。
「教材の意図を知りたい」「『けんきゅう』『かいはつ』『じっけん』の違いって何?」というところを、この記事で解説していきます!
今月号のテーマは「風」。
「教材の意図を知りたい」「『けんきゅう』『かいはつ』『じっけん』の違いって何?」というところを、この記事で解説していきます!
教材の意図
教材紹介の動画です
「水は低い方に流れていく」「鉄は熱を伝える」
こうした科学法則は言葉で言われるよりも、実際にアプリの中で自分で動かして体感することの方が、学習体験として子どもたちの中に強く残ります。
「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」は、風、水、熱、電気等をテーマにした実験シミュレーションを、新鮮な驚きとともに楽しめる教材です。「当たり前」が自分の中に構築されていない年代だからこそ、そうした経験が、学校で改めて科学法則を知識として学習したときの支えとなり、体験をともなった知識として蓄積されていきます。
「けんきゅう」「じっけん」「かいはつ」の違い
チャンネルに入ると、「けんきゅう」「じっけん」「かいはつ」の3つのゾーンがあります。

「けんきゅう」は答えとその手順がある程度決まっているもの、「じっけん」はゴールは用意されているけれどプロセスは自由なもの、「かいはつ」は「どうしたいか?」を自分で決められるものというように、段階的に自由度が上がっていく設計です。
けんきゅう:答えのあるもの

「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」を開いたら、まず「けんきゅう」をやってみましょう。各アイテムがどのような作用を持っているか、徐々にレベルアップしていくステージを通じて、達成感を積み上げながら学ぶことができます。それぞれの要素がどのように動くかを通じて、現象を感覚的に理解することができます。
ステージが進むにつれて、「ひと目でわかる!」というものから「どうすればいいんだろう?」と深く考えさせる問題になっていきます。動かせるアイテムが増え、アイテムの仕組みを連動させたり、複数の法則を関連付けて考えることが必要になります。
全部解けないといけないというものではありません。途中まで進めたら、「じっけん」に進んでいただくのもおすすめです。
じっけん:ゴールはあるが、プロセスは自由なもの
「けんきゅう」をある程度進めると、「じっけん」で使えるアイテムが増えていきます。「じっけん」では、「水をたくさん貯める」「風船をたくさん割る」「氷をとにかく溶かす」といったシンプルで爽快感のあるお題が提示されます。
「けんきゅう」とは違い、お題を達成するためのやり方は一通りではなく、工夫のしがいがあります。スコアとそれに応じたメダルというかたちでアプリ側からもフィードバックがあり、「次はこうしてみようかな?」という試行錯誤を自然と後押しできるようになっています。
かいはつ:決められた答えのないもの
「こうやったらどうなるんだろう?」をなんでも試せる場所として「かいはつ」は設けられています。自分の中で「こうしたい!」が芽生えたときに、それを全部やれるように、という思いから生まれたものです。絶対にやらないといけない課題というわけではありません。「かいはつ」には時間制限がないので、こういったものが好きな子は熱中し過ぎてしまうことも時にはあるかと思います。熱中できることは素晴らしいことですが、時間を守ってほしいときもありますよね。そんなときの声かけには、注意が必要です。
途中で無理に止められると、他の教材に対しても「また途中で止められるかもしれない」と消極的になってしまうかもしれません。保護者の方から見て夢中になり過ぎているなと感じた際には、別の日に改めて、「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」を開く前に、「こっちもやってみようよ」と別の教材に意識を向ける声かけがおすすめです。