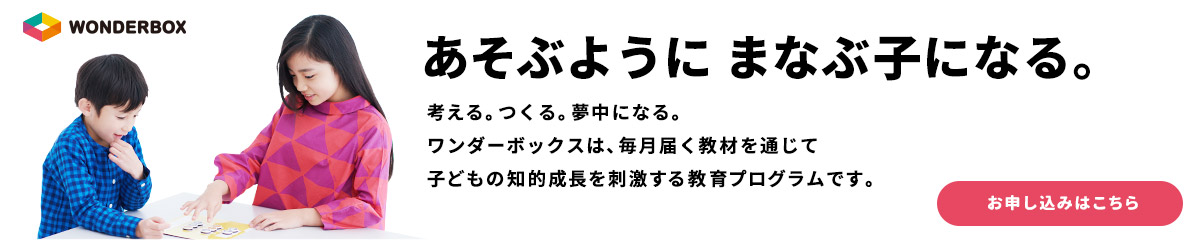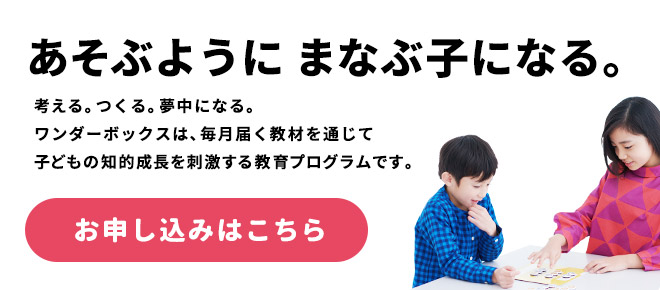今月号のトイ教材は「テクロンのけんきゅうりょこう」です。
アプリ教材「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」でおなじみのテクロンのアクリルスタンドが付属します。
構造力学と言うと大げさかもしれませんが、「丈夫にするには?」「水に浮かべるには?」「バランスをとるには?」といったテーマで、テクロンと一緒に紙を使って実験してみましょう。

それぞれの「けんきゅう」の意義
「はしのまち」
テクロンが乗っても壊れない、丈夫な「はし」を紙で作ります。


折る回数を増やしたり、形状をギザギザに変えたりと、折り方を変えるだけで強度が変わることを、実際に手を動かして実感できます。
冊子の中で、「ダンボールの中が三角なのは、丈夫にするため」という事例を一つ紹介していますが、例えば橋で使われる三角のトラス構造や、蜂の巣のハニカム構造等、「じゃあこのかたちにも意味があるのかな?」と身近なもののかたちに目を向けるきっかけとなれば嬉しいです。
「ふねのまち」
銀紙で「ふね」を作って水に浮かべてみましょう。

形を工夫することで、紙でも水に浮かぶものが作れて、ある程度の重さにも耐えることができるというのは、子どもたちにとっては「意外」なこととして体感できます。
浮力というのは、水を押しのける力と、その水から押し返される力の釣り合いによって生じるという知識を言葉で説明される前に、自分で船を作って試行錯誤することで、それを「体験を伴った知識」として身につけることができます。

けんきゅうポイントでは、試して体感したあとの「なぜだろう?」にこたえるものとして、解説を入れてあります。これを読むことで、「じゃあこれはどうなんだろう?」と新たな知的好奇心が芽生えることを願って、伝わりやすい表現を工夫しています。
「タワーのまち」
丈夫さとバランスの両立をめざします。


紙はそのままでは立たなくても、折り曲げたり丸めたりすれば立つのだ、という気づきを得た上で、どうすればより高いタワーにすることができるかを研究します。
「タワーの上にテクロンを乗せなければならない」という制約の中でいかにバランスの良いものにするか、ということにおいて様々な方法・組み合わせが考えられるため、工夫のしがいのあるミッションです。
教材開発者が伝えたい、お子さまと一緒に取り組む際のポイント
大人から見れば「失敗」でも、子どもから見れば「発見」
例えば「タワーのまち」でタワーを作るとき、子どもは絶対立つと思っているけれど、見るからに立ちそうもないものを作っていても、「それじゃ立たないよ」と言わずに見守ってあげてください。
「立つと思っていたけど倒れた」という「発見」から、「次はどうするか?」を自ら考え学ぶ機会を大切にしたいと、私たちは考えています。紙の角と角をあわせる、まっすぐ折るといった作業的な部分は、お子さまがそれによってもどかしい思いをしていそうであれば、サポートしてあげてください。
家にある紙もどんどん使って!
予備の紙も付属していますが、「色々試してみたい!」となったときは、家にある新聞紙やチラシやコピー用紙等、使っても構わない紙でどんどん素材の違いを楽しんでみてください。丸めてみたり、たくさん折ってみたりしたらどうなるんだろう?といった好奇心の赴くままに、たくさん実験・研究してみていただけたら嬉しいです。「紙だけでこんなに遊べる!」という経験を通して、身の回りのものの「かたち」の不思議にまで思いを馳せるきっかけとなることができれば幸いです。