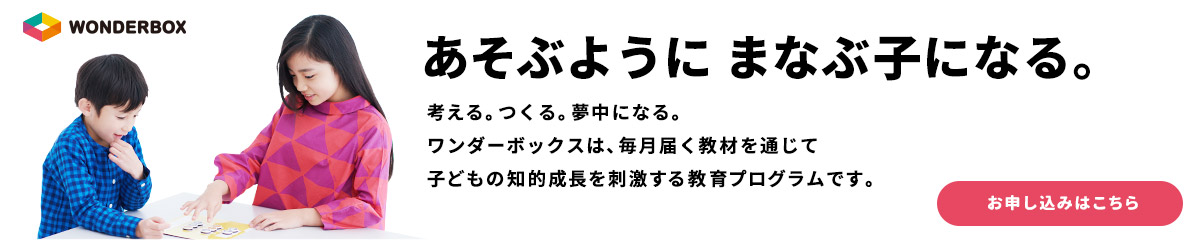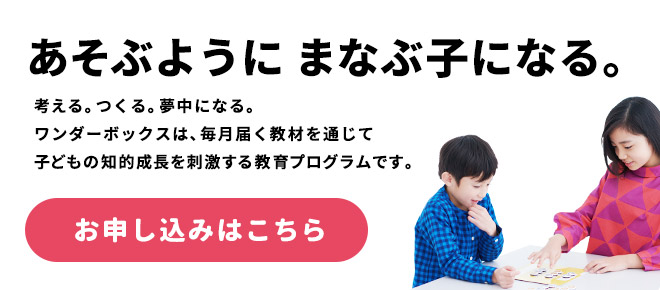2024.03.22
紙教材の良さって何?紙教材とアプリ教材それぞれの意義についてお伝えします
「アプリでできることを、わざわざ紙と鉛筆でやる意義はなにか」というご質問をいただくことがあります。私たちは、アナログ教材とアプリ教材はそれぞれに良さがあり、どちらかだけで子どもの知的わくわくを最大限に引き出すことはできないと考えています。
今回の記事では、アナログ教材で思考力問題に取り組む意義と、ワンダーボックスのアナログ教材とアプリ教材の補完しあう関係 について、思考力ワークブック「ハテニャンのパズルノート」を題材に解説していきます。
紙(アナログ教材)で思考力問題に取り組む意義は?
紙の良さは、「逸脱」にあります。ここで言う逸脱とは、自由な探究のことを言います。
「鉛筆で濃淡のある印をつける」「切って試してみる」「ゴールや途中から解いてみる」など、予定されていないやり方で自由に試行錯誤することができます。

こちらは、実際に私たちの研究授業で子どもたちに解いてもらった問題です。
書いたり消したり、ルール上通ってはいけないところも行ってみたりと、答えに直接結びつかないこうした手間は、子どもにとって「不便さ」のように感じられるかもしれません。
ですが、手間があるからこそ、例えば間違ったものを消す時にも「どこまでは合ってるか等を考えながら消す」「この辺がどうも怪しいとあたりをつけてから消す」といったように、考えながら問題を解こうとする動機になります。
紙だからこそ自由に試せる良さは、問題を解く時だけでなく、問題を作る時にも発揮されます。実際に子どもたちが作ったものをご紹介しながら説明していきます。
これらは実際に子どもたちが作ってくれた問題です。どちらも、教材作成者の意図を超えて子どもたちが自由に試行錯誤をした結果です。
1枚目の問題は、問題自体の形も枠にとらわれず、それでいて星のそれぞれの区画が迷路としての役割を果たしており、左側に難易度設定まで書いてある遊び心のある問題です。
2枚目の問題のようなものをお子さまが作っているのを見ると、少し心配になることもあるかもしれません。ですが、適当に作っているのではなく、純粋に「こうした方がおもしろいのでは?」と教材作成者側の意図を超えた工夫をしていることもあります。

アプリ教材では、入力できる範囲とそれに対する反応はある程度決まったものになります。例えば、アプリ教材では「どこに線を引くことができるか」「どんなアレンジができるか」も開発者が用意した範囲内でしか試行錯誤できません。
ですが紙ならば描画の範囲、追加ルール、何を「ゴール」「目標」とするかも何かにとらわれることがありません。子どもたちの発想をそのまま表現できるアナログ教材で問題を作ることには、そうした「程よい余地」を残しておきたいという意図があります。

問題と関係なさそうなことをしていると、保護者としては「問題の指示通りに解いてほしい」という気持ちになるかもしれません。ですが、ワンダーボックスの教材では、「これを試してみたい」という好奇心の芽生えとその試行錯誤も「知的なわくわくの時間」ととらえています。
自ら課題を見つけ、自分なりのやり方を模索していく経験を積むことは、思考が柔軟で何にでも興味を持てる時期だからこそ大切です。
好奇心を育てる場と、緻密な思考が求められる問題に向き合う場、ワンダーボックスにはどちらも用意されています。
アプリ教材とアナログ教材が両方あるのはなぜ?
アプリ教材には、「アニメーションや音でのガイドが豊富で、『何をすればいいか』がわかりやすい」というメリットがあります。これと対比すると、アナログ教材には、「自分なりに一からルールを考え、実際に試行錯誤する力が養われる」というメリットがあります。

このように、ワンダーボックスでは、アプリ教材とアナログ教材はそれぞれに違った良さがあります。
例えばアプリ教材の「シンクシンクプラス」の得意な問題をやって自信をつけてから、より自由度の高いトイ教材や「ハテニャンのパズルノート」に挑むのも良いですし、紙で自由な試行錯誤を楽しんでから、アプリ教材でサポートを受けながらより深い知的なわくわくを楽しんでも良いでしょう。
アプリ教材とアナログ教材が両方あるからこその体験を、ワンダーボックスではこれからもお届けしていきます。教材について何かご質問がある場合は、カスタマーサポートよりいつでもお問い合わせください。