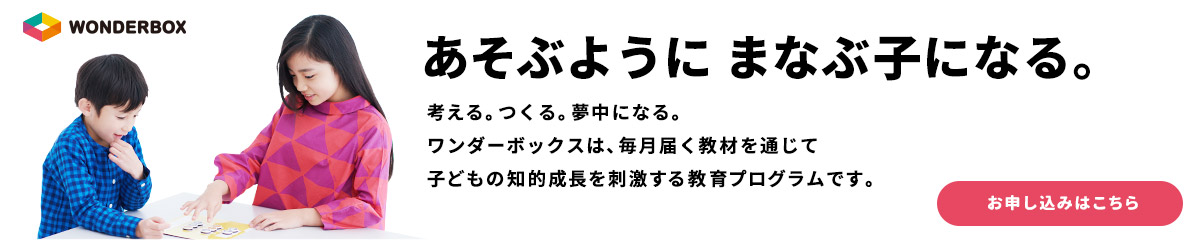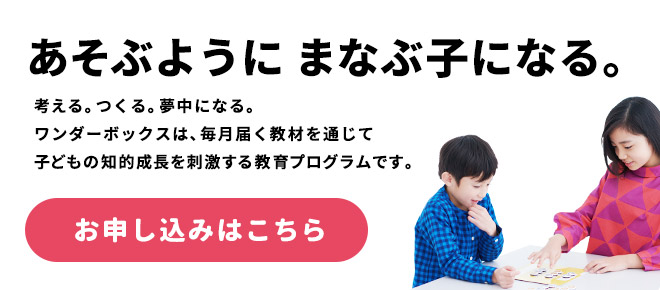「かさねてクリア」は素材の持つ「透明さ」をいかして、透けて見える・重なって見えることを通して図形への興味を引き出す教材です。「透ける」「重ねられる」「ずらして変化の過程を楽しめる」クリアシートの特性を活かした遊びに取り組みます。
クリアファイルやビニール、ペットボトル等、透明な素材は身の回りにたくさんあります。身近なもので、紙とはまた違った新しい体験ができる面白さを「かさねてクリア」では大切にしています。
今回の記事では、「『かさねてクリア』でどんな力が育まれるか」「取り組み方のヒント」について解説していきます。
テーマ「どうぶつ」の教材の意義と取り組み方のヒント

テーマ「動物」では、雑多な図形の集まりが、はっきりとした意味のあるかたちに一瞬で変わる驚きを味わうことができます。
シートをどこで合わせれば良いのかを探る過程で、うまく重なりそうなシートの向きを判断できる図形認識力と、位置を合わせる手先の器用さが培われます。

これで答えがあっているのかな?と思った時

問題冊子の裏表紙の下部に答えが掲載されていますので、ご活用ください。
ヒントの出し方がわからない時
まず、「りくのシート」「うみのシート」のどちらを使うかが合っているかどうかを確認してあげてください。
合っていたら、「シートをもっとゆっくり回してみるのはどうかな?」と回す速度を変えてみたり、「ここに重ねて回してみたら?」と大まかな場所を教えてあげるのもよいでしょう。
合っていたら、「シートをもっとゆっくり回してみるのはどうかな?」と回す速度を変えてみたり、「ここに重ねて回してみたら?」と大まかな場所を教えてあげるのもよいでしょう。
テーマ「かたち」の教材の意義と取り組み方のヒント

テーマ「シャツ」では、同じ図形の組み合わせでも、図形同士の重なり方の違いで全く異なる印象の模様に変化するおもしろさを味わうことができます。
「ここが重なればきれいな模様になりそう」という見当をつける過程で、自然と図形認識力が培われます。

ヒントの出し方がわからない時
前提として、どの模様が見つけやすいかには、個人差があります。お題の紙に書かれている順番通りに探す必要はありません。4歳から8歳くらいまでの子どもの特性として、集中すると視野が極端に狭くなり、細かいところだけを見てどつぼにハマるというケースがよくあります。
ずっと同じところを繰り返していそうなときには、「ちょっと離れて見たらどう見えるかな?」と声かけをしてみると、それがきっかけで俯瞰して探すことができるかもしれません。
以上、「かさねてクリア」のテーマの紹介でした。
この教材はテーマを変えてまた登場する予定ですので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
ずっと同じところを繰り返していそうなときには、「ちょっと離れて見たらどう見えるかな?」と声かけをしてみると、それがきっかけで俯瞰して探すことができるかもしれません。
以上、「かさねてクリア」のテーマの紹介でした。
この教材はテーマを変えてまた登場する予定ですので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。