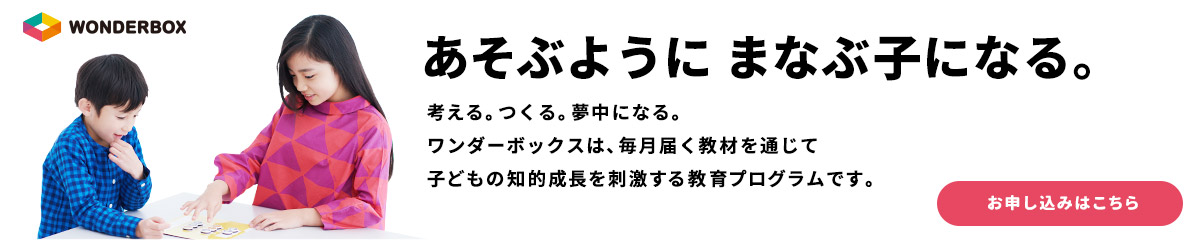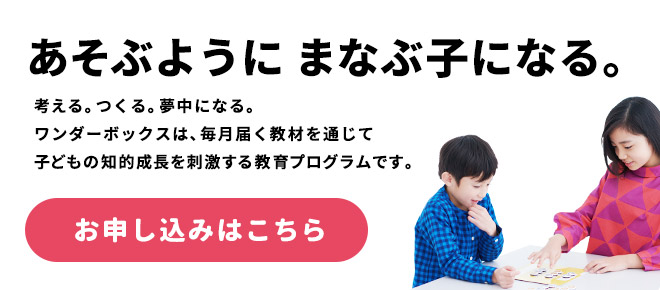2024.03.22
「作問があるのはなぜ?」ハテニャンのパズルノートの開発者がお答えします。
教材をしる
毎月届く思考力ワークブック「ハテニャンのパズルノート」ですが、「どう使えばいいの?」「問題を作るパートが入っているのはどうして?」と感じている保護者の方もいらっしゃるかと思います。
パズルノートでどういった体験を子どもたちに届けたいと私たちが考えているか、この記事を通してお伝えできればと思います。
「ハテニャンのパズルノート」とは?
ハテニャンのパズルノートは、パズルや迷路について、試行錯誤しながら問題を解く楽しさに加えて、問題を作り出す体験を提供する教材です。


問題を「解く」
パズルノートの前半部分では、厳選された思考力問題の中から、紙だからこそ試行錯誤しやすい問題群に取り組みます。
なるべくひと目で伝わる直感的なデザインと、ルールとしてシンプルでありながら問題としての奥深さとアレンジが効く発展性を備えた問題を通じて、「考えることの楽しさ」を伝えられたら、という私たちの思いが込められています。

「解く」部分に関しては、スモールステップで「わかった!」を着実に積み上げられるように設計されているので、「一気にやってしまって物足りない」という方もいらっしゃるかもしれません。毎日コツコツという使い方もできますが、一気にやってしまうことは決して間違った使い方ではありません。意欲の湧いているうちに、その子にとって適切なスピードで走り切れたということで、問題の全体像をつかむことに役立ちます。
ボーナス問題について

「ボーナス問題」は大人でも迷うような難易度の高い問題を収録しています。全ページの網羅することよりも、「やりたい!」という意欲を持って取り組めることが大事です。
問題を「作る」

パズルノートの後半部分では、問題を「解く」側から問題を「作る」側への視点の移動を促す問題が徐々にあらわれるという構成になっています。
パズルノートでの最終目標は、「与えられた問題を正しく解くこと」だけではなく、「どうすればこの問題を面白くできるかを考えること」です。
「問題を作る」ときいて、「パズルのワークブックなのに、どうして”未完成”の問題が入っているのだろう?」と思った方もおられるかもしれません。
しかし、「自分で作る」といった体験が、考える力を養うためにいかに効果的かということについて、説明させてください。
しかし、「自分で作る」といった体験が、考える力を養うためにいかに効果的かということについて、説明させてください。
「問題を作る」という体験の中で最も大事な要素は、「解く人のことを考えながら問題を作る」ことです。「ここで迷うだろうな」「ここは簡単にいけるかもしれない」と考えながら問題を作るという体験は、他の人の作った問題を解くときにも活かされます。
自分で問題を作る過程を経ることで、「この問題を作った人は、どういうことを意図しているのだろう?」ということを考えながら問題を解けるようになります。パズルノートを通じてそのような考える力が身についてほしいと願って、私たちはこの教材を開発しました。

パズルノートのアプリで、「ハテニャンにお便りを送る(ハテニャンに問題を見せる)」「掲示板で他の子の問題を見ることができる」といった要素を入れているのも、問題を「誰かに見せるもの」として作ってほしい、問題を作る上で他の子の視点にもふれてほしいという意図があります。
ですが、誰かが自分の問題を見てくれたという体験にまさるものはありませんので、もしお子さまから「解いてみて!」と問題を見せられたら、一緒に解いてあげてください。
どのように解いているかという様子そのものが、お子さまにとって「次はこうしよう」という意欲のきっかけになります。
「ハテニャンのパズルノート」の取り組みの参考になれば幸いです。
こちらの記事では、パズルノートの「困った!」におこたえする、お子さまへの声かけ例をご紹介していますので、合わせてご覧ください。
こちらの記事では、パズルノートの「困った!」におこたえする、お子さまへの声かけ例をご紹介していますので、合わせてご覧ください。