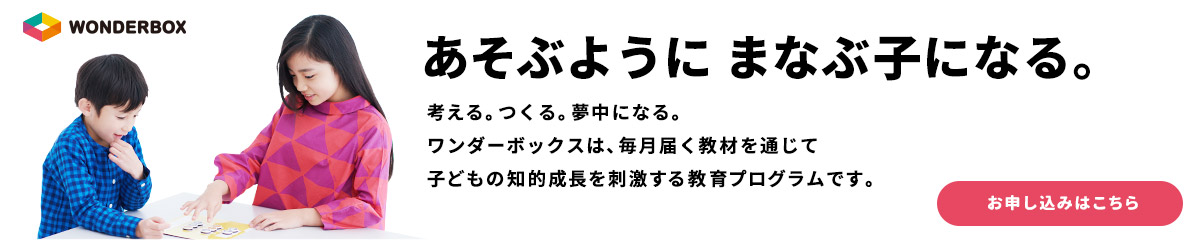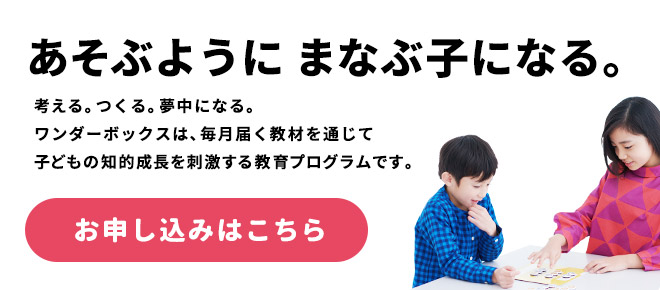「タブレットを使った学習は、子どもは好きみたいだけど、親としては視力への影響が不安…」というお声を保護者の方からよくいただきます。子どもの視力は一生ものだから、親が気をつけてあげないと、と不安になるのはもっともです。
今回は、「何が視力にとって大事か」を踏まえたうえで、これからのタブレットとの付き合い方のポイントをご紹介します。
タブレットと視力に関する誤解
タブレットの画面を見ている時間と近視については、特異な因果関係が立証されているわけではありません。(*1)
視力にとって大事なのは、見ているものの材質ではなく、目と対象物の距離です。
例えばノートからの距離が15cmの状態で30分間勉強する場合と、タブレットからの距離が15cmの状態で30分間使用する場合では、視力への影響に大きな違いはありません。(画面のブルーライトが睡眠リズムに影響する場合はあるので、使用する時間帯には注意が必要です)
タブレット「だから」特別に目に悪いということはなく、以下の注意点を意識していれば、視力への負荷は紙と鉛筆を使った学習と変わりません。
日本眼科医会のHPで、子どもの目の健康の啓発活動の一環として掲載されている注意点
- 目線があがるように画面が立つスタンドのようなものを活用する
- タブレットから30cm以上、目を離す
- 机の上にタブレットを置き、椅子に座って使用する

「使い過ぎ」を防ぐための親子の約束
タブレット等のICT技術を活用した機器は、子どもたちの世代にとって「あって当たり前」になっていきます。
「スマホやタブレット等を自在に扱えて、それでいて使いすぎない」といったICTリテラシーを、家庭で培う機会があることは、安全な練習の場があるということでもあります。
家庭でトラブルなくタブレットを扱うには、親子での約束が不可欠です。次に、そのポイントを紹介していきます。
「約束」のポイント
1. タブレットの所有権
●保護者のタブレットを貸している場合
●保護者のタブレットを貸している場合
保護者のタブレットを借りている、という意識が子どもにあれば、親と子の間での約束に子どもが納得しやすくなります。
また、教材に取り組んでいる様子を見守ることで、「この教材はこれくらい時間がかかるんだな」という目安が親子で共有できていれば、実状に即した約束を作りやすくなります。
●既に子どもが自分のタブレットを持っている場合
一度子どもに管理を任せたものは、子どもの自主性を尊重しつつ、最低限のルールを決めておくと良いでしょう。
いつタブレットを取り上げられるかわからない、という状況では、子どもの方でも頑なになってしまう場合があります。大切なのは、気分良く「おしまい」にできるための約束です。
いつタブレットを取り上げられるかわからない、という状況では、子どもの方でも頑なになってしまう場合があります。大切なのは、気分良く「おしまい」にできるための約束です。
例えば、「30分以内に終わることができなかったらペナルティ」といったやり方よりも、「タブレットの時間が終わったらおやつの時間」「次にタブレットを使えるようになる時間を決めておく(次いつできるかわからない状況にしない)」といったように、気持ちよく終われるメリットを用意するやり方がおすすめです。
ワンダーボックスのアプリでは、「保護者メニュー」から1日の使用時間を設定できます。
お子さまの目の健康や、楽しんで取り組み続けるためのメリハリを配慮し設計されており、安心してアプリ教材に取り組めます。保護者が忙しくて直接声かけできないときでも、アプリが自動で「約束」を守るお手伝いをしてくれます。

設定した時間ごとに、アプリ側から休憩・終了時間を提示します。保護者メニューの鍵が九九の入力なので、保護者がいなくても保護者メニューに入れてしまう場合があります。その時は、独自のパスコードを設定できますので、ご活用ください。
※一定時間の継続が必要な教材では、お子さまの集中を妨げないように、途中で休憩・終了しない設計にしています。
私たちが実施している研究授業(*2)でも、15〜20分に1回はタブレットから目を離す時間を設けています。目を休める時間は大事ですので、「おやすみ機能」を設定される際の参考にしてみてください。
アプリだからこその可能性
紙でやることに意義がある教材もあれば、アプリだからこそイメージしやすい教材もあります。
思考力教材の「シンクシンクプラス」で、立体を画面上に再現できるのはアプリならではの強みです。紙ではイメージしづらいものも、三次元で捉えて、自分で動かせるからこそ、空間認識力が育まれます。
サイエンス教材の「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」は、リアルでは再現に手間がかかる実験のシミュレーションを、アプリで思う存分楽しむことができます。
サイエンス教材の「テクロンとひみつのけんきゅうじょ」は、リアルでは再現に手間がかかる実験のシミュレーションを、アプリで思う存分楽しむことができます。
ワンダーボックスでは、アプリの強みを活かした教材をこれからもお届けしていきます。それぞれのご家庭に合ったタブレットとの付き合い方を模索しつつ、楽しんでもらえますと嬉しいです。
よくあるお悩みQ&A
Q1. ワンダーボックス以外のアプリやYouTubeを開いて、そればかり見ており、ワンダーボックスの教材に取り組みません。
A1. タブレットを使用する際のルールをお子さまと一緒に話し合ってみましょう。
保護者が一方的にルールをつくると、「自分の意見を聞いてもらえなかった」と子どもが納得感を持ちにくいので、少し時間はかかるかもしれませんが「どういうルールがいいか一緒に考えよう」と話し合うのがおすすめです。
また、タブレットによって設定方法は異なりますが、「ペアレンタルコントロール」機能を使ってお子さまが閲覧できるアプリを制限したり、利用時間を制限することができます。「(お使いになっているタブレット機種名) ペアレンタルコントロール」で検索するとやり方がでてきますので、ぜひあわせてご活用ください。
Q2. 幼少期からタブレットに触れるのは刺激が強すぎて、ゲーム依存症にならないか心配です。
A2. 過度な演出ではなく、「考える楽しさ」でやる気を引き出します。
アナログでは見受けられないような強い報酬意識や刺激をデジタルは抱えており、それがアナログを楽しめなくなる一因や依存症につながってしまう原因となっていると言われています。
ワンダーボックスでは、ポイントやスタンプといった演出での動機づけは必要最低限に抑えています。そのうえで、より学びにとって本質的な「解ける喜びや考えることのわくわく」を感じられることを重視して教材を設計しています。
(*1)参考:吉川徹(2020)『子どものこころの発達を知るシリーズ10 ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち: 子どもが社会から孤立しないために (子どものこころの発達を知るシリーズ 10)』合同出版 Lanca, C. & Saw, S. (2020) The association between digital screen time and myopia: A systematic review. Ophthalmic Physiol Opt 40, 216–229 (*2)ワンダーファイでは、少人数での研究授業を定期的に行い、教材開発に携わる問題作成者、エンジニア、デザイナーが直接子どもたちからフィードバックを得られる場として教材開発にも取り入れています。