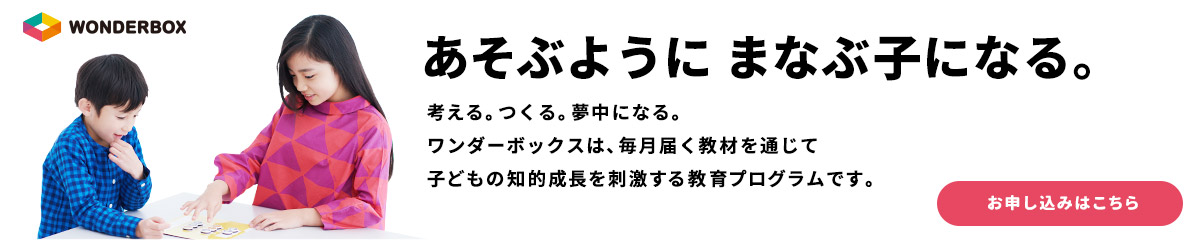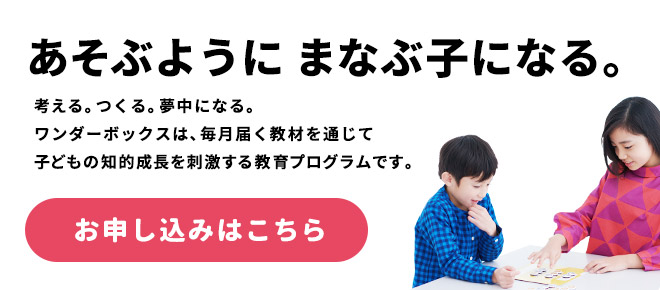サイエンス教材「ケミーのじっけんマップ」のテーマは「金属の抽出」。
金属の入った化合物と様々な液体を混ぜ合わせて、純粋な金属を取り出します。
今回の記事では、「実際にアプリで何をやるのか」と、もっと知りたいお子さま向けの動画を紹介いたします。


アプリでどんなことができるの?
「ケミーのじっけんマップ」では、「そざい」を2つまで組み合わせて、それに「わざ」を使います。
今回のテーマでは、複数の金属が混ざりあったものから、金・銅・鉄を取り出します。
例えば、鉄と銅が混ざった「ぎんいろのきんぞく」と「かせいソーダ」をあたためると、鉄ができます。
わざの中には「でんきぶんかい」等、中学校の化学で習うようなものもありますが、事前知識は必要ありません。
例えば、教科書で習うことと、ケミーのじっけんマップでそれをどう表現しているかの違いを図で示すとこうなります。
教科書では、「硫化銅水溶液を電気分解すると、陰極板に銅が析出する」と習いますが、「ケミーのじっけんマップ」では「あおいろのえきたい」を「でんきぶんかい」したら銅ができた、というように簡略化しています。
6〜8歳頃の年代では、「正しい知識を身につけること」よりも、擬似的に経験して、体感してみることのほうが得意です。後に学校で習ったときに、「ふれたことがあるもの」と思えることで、学びがより身近になります。
純度の高い貴金属を抽出する技術として始まり、更には鉄や鉛を黄金に変えることを夢見た錬金術の試行錯誤の積み重ねは、化学という分野の発展に貢献してきました。
「金属の抽出」というテーマで、お子さまが化学の面白さの一端にふれることを願っています。
マップからゴールまでの過程を考えてみたり、寄り道してみたりと、自由な探究を楽しんでみてください。
もっと知りたいお子さま向けの動画紹介
hakaihan.”フリスク缶に銅メッキをかけてピカピカに磨いてみた”.Youtube hakaihan 参照:2025年1月30日
「電気分解で銅ができることが何の役に立つの?」という疑問におこたえできる動画です。電気分解の仕組みを使った「電気めっき」でフリスク缶をピカピカにめっきしています。動画の8:00ごろから、実際にめっきをしている様子を見られます。
Gold Recovery."World's Biggest Gold Recovery on Youtube | 250 KG Ceramic CPU Processors Gold Recovery". Youtube Gold Recovery 2021年.※参照:2025年1月30日
動画の言語は英語ですが、CPUから金を抽出する過程がわかりやすく動画になっています。
今回登場する金・銅・鉄は、身の回りの色々なところに使われています。金はスマホを含む多くの精密機器の基盤に、銅は10円玉に、鉄は家や車にと、身近なところでどんなものに使われているか、ぜひ探してみてください。
NHK for School (2023-02-13参照) ※リンク先で動画が見られます。
人類が金属をどのように活用してきたか、なぜ「金」の利用は歴史的に早かったのかということを1分以内で解説している動画です。
以上、「ケミーのじっけんマップ」新テーマの紹介でした。
教材に関して気になる点がございましたら、こちらからお気軽にご連絡ください。