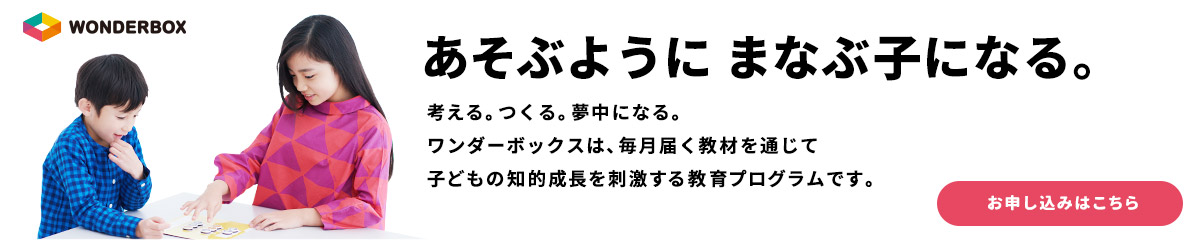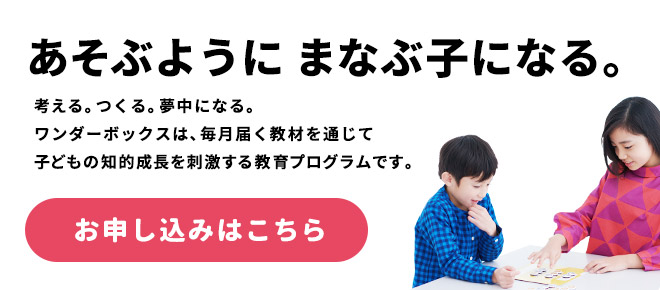Vol.アクアマリン(9月号)の6歳〜(小学生)向けサイエンス教材「ケミーのじっけんマップ」のテーマは「ペニシリン」。
腐った食べ物にはえている青カビが、様々な化学反応を経て、細菌を抑制する抗生物質になる過程を体験できます。
この記事では、「実際にアプリで何をやるのか」と、「なぜ『みかん』と『木のえだ』なのか?」といったことについて解説していきます。


アプリでどんなことができるの?
「ケミーのじっけんマップ」では、「そざい」を2つまで組み合わせて、それに「わざ」を使います。


例えば、「木のえだ」を「あたためる」と炭になったり、「みかん」を「じゅうそうすい」につけるとどろどろになったりします。
今回の実験で行うペニシリンの精製は、大まかに言うと「青カビの培養液を炭とまぜて、炭にペニシリンを吸着させ、酸性の酢でアルカリ性の不純物を取り除き、重曹水でペニシリンを炭から溶け出させる」といったものです。(ペニシリンの精製には本来もっと工程がありますが、省略しています。)
これらの事前知識が必要というわけではありません。何かを組み合わせると化学反応が起きる不思議さを体感して、好奇心が育まれることがこの教材の趣旨です。
アプリでの実験を通して、現象への興味が引き出された状態であるほうが、教科書で知識を学んだ際により印象的なものになります。
なぜ「みかん」と「木のえだ」?

この2つが「身近なもの」であることが理由のひとつです。
化学反応は身近なものでも頻繁に起こっているという実感をもってもらえるよう、「ケミーのじっけんマップ」では身近なものを題材に取り上げることがあります。
みかんにカビが生えてしまった、という経験はどこのご家庭でもよくみられることかと思います。みかんは本来保存のきく果物なのですが、みかんの皮に含まれる「プロリン」というアミノ酸が特に青カビの発芽を促すため、「青カビの生えたみかん」がよくみられます。
身近なものからペニシリンが精製できる、という題材でSF時代劇の「JIN−仁−」という作品で江戸時代にタイムスリップした医者がペニシリンで患者を救う描写があったりします。
(実際には、身の回りのものでこうした実験を行うと、他の細菌が入り込むリスクを避けられないといった危険性はあります。)
以上、「ケミーのじっけんマップ」新テーマの紹介でした。
今月号も楽しんでいただけますと幸いです。